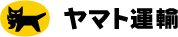2025.07.04 コーヒーの読み物
ホンジュラス カップオブエクセレンス 2025 全ロットカッピング

ティピカの逆襲──2025 ホンジュラスCOE、衝撃の頂点
先日、ホンジュラスのカップ・オブ・エクセレンス(COE)2025年大会の入賞ロットをカッピングする機会がありました。今年のホンジュラスCOEは、例年と比べてさまざまな点で特徴的でしたが、入賞ロットの完成度は非常に高く、品種や地域の多様性を体感できる、学びの多いセッションでした。
今年のエントリー数は190ロットに激減
例年ホンジュラスでは300ロット以上のエントリーがありますが、今年は190ロットと大幅に減少しました。
この背景には、現在の高止まりしたコーヒー相場があるとされています。
「すぐに現金が必要な生産者は、審査に時間がかかるCOEを敬遠し、市場に売ってしまうケースが多かったのではないか」
— ワタル 松元氏(COEヘッドジャッジ)
落選のリスクと販売までの時間をかけてでもチャンスをつかみに行くか、すぐに現金化するか——生産者の選択がエントリー数に大きく影響した年でした。
エントリーから入賞までの流れ
集まった190ロットのうち、まずスコア86点以上の76ロットが国内審査ラウンド1に進出。そこから53ロットに絞られ、さらにラウンド2で再度評価。35ロットが国際審査へ進出し、最終的に30ロットが入賞となりました。
これを見れば入賞までには、国内外の審査員による厳正な審査を何度も通過しなければならず、『COE入賞』というのは、どれだけ大変なことかが理解していただけるでしょう。
審査は3部門に分かれて実施
トラディショナル・バラエティズ部門
ティピカ、ブルボン、カツーラ、カツアイ、パカス、イカフェ90、レンピーラなど。
パライネマ部門
ホンジュラス独自のハイブリッド品種「パライネマ」に特化。これは、国内機関IHCAFEの強い意向によって設けられた、いわば“国の戦略”が反映された重要部門です。
エキゾチック・バラエティズ部門
ゲイシャ、パカマラ、マラカツーラ、SL28など、個性の強い希少品種が対象。
こうした部門分けにも国ごとのコーヒー政策や品種戦略が反映されているというのもCOEを見ていくうえで面白さのひとつです。
地域別ではサンタバルバラが圧倒的
エントリーロットの地域分布を見ると、サンタバルバラ県からの出品が110ロットと、全体の半数以上を占めていました。
| 地域 | エントリーロット数 |
|---|---|
| Santa Barbara | 110 |
| La Paz | 17 |
| Lempira | 15 |
| El Paraíso | 14 |
| Intibucá | 14 |
| Francisco Morazán | 9 |
| Olancho | 2 |
最終的に、入賞ロット30のうち22ロットがサンタバルバラ産という結果に。
「サンタバルバラでは過去に入賞経験のある農園が多く、COE=チャンスという意識が根づいている。審査に時間がかかっても、それに見合う価値があると生産者たちが判断しているのでは」
— ワタル 松元氏
これは単なる地域の強さではなく、COEへの理解と信頼の差とも言えるかもしれません。
カッピングの印象〜3部門を通じて〜
トラディショナル・バラエティズ部門
この部門で最も驚かされたのは、1位に輝いた「Finca Dariela」のティピカ ナチュラル。
今や絶滅危惧種くらい希少になったティピカがトップを取ったこと自体、感慨深いものがあります。
カップは複雑でクリーミーなテクスチャ、豊かな果実のフレーバーに満ちた驚愕の出来。クラシックな品種の力強さとエレガンスを再認識させてくれました。
パライネマ部門
1位は、なんとサンタバルバラ県のEl Rubí。
ホンジュラスでは「最高のパライネマはエル・パライソ県で採れる」というのが“常識”です。サンタバルバラ産が1位を獲得したのは正直私にとっては驚きです。
もっとも、本当に尖ったパライネマは「ベスト・オブ・パライネマ」に出品されているため、パライネマに興味がある方はそちらのロットもぜひ飲んでみてください。
エキゾチック・バラエティズ部門
この部門は、もはやゲイシャのためにあるような部門。実際、入賞ロットのほとんどがゲイシャで、その他はパカマラ、SL28、マラカツーラが各1ロットずつ。
個人的にゲイシャにはあまり強い興味がないのですが、そんな中で最も心に残ったのが7位「El Leona」のパカマラ ナチュラル。
ボリューム感がありながらもクリーンで、南国フルーツのような甘さとバランス感に優れた素晴らしいロットでした。(じつはこの農園は、昨年も入賞しています)
まとめ
今年のホンジュラスCOEは、エントリー数の減少、サンタバルバラの圧倒的な存在感、そして国ごとの戦略がにじむ部門構成など、単なるコーヒーコンテスト以上の“背景”が見えてくる大会でした。
それでもなお、入賞ロットはどれも素晴らしく、特にティピカやパカマラといった品種の再評価が進んでいることは希望でもあります。これからもカップを通じてまた新たな物語が広がっていくことを楽しみにしています。