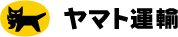2025.10.11 生産者特集
ママミナ農園 ― 霧と光のあいだに

名前に刻まれた家族の物語
ニカラグア中部、マタガルパの美しい山々に抱かれるようにして、Mama Minaは佇む。
一日の6割を霧が覆うという特異なミクロクリマ。湿潤な空気と、雲間から差し込む陽光。その繰り返しが、ふくよかで甘みを帯びたコーヒーを育んでいます。園内には花々が咲き誇り、多様な生態系が織りなす景観は、20年にわたり数多くの農園を見てきた中でもトップクラスの美しさです。
かつては「ラ・ミニータ」と呼ばれていたこの農園。しかし、コスタリカに同名のブランドが存在したため、新たな名を探すことになりました。そこで彼らが選んだのが「Mama Mina」。曽祖母ミルナ・マキューアンを称えて冠した名です。家族の歴史と敬意を刻み込む改名には、土地や作物への責任、そして「家族と共にある農園」というミエリッシュ家の価値観が映し出されています。
その「家族の歴史」の中には、若くしてこの世を去ったエレアンの記憶もまた深く息づいています。
彼女が農園を歩き、未来を語り、共に雨を待ったあの日──その時間は、ママミナの畑に抱かれ、いまも光を灯し続けています。ミルナへの敬意とともに、エレアンの存在もまたこの農園の物語に組み込まれ、世代を超えて受け継がれていくのです。
雨を待つ時間の記憶
ママミナを初めて歩いた日、私は亡きエレアン、そしてお父さんのDr. エルビンと共にいました。雨に備えてと、エルビンが私のために長靴を買ってくれ、それを履いてぬかるむ畑へと足を踏み入れました。汗ばむほどの日差しの下、コーヒーの木々のあいだを歩き続け、お腹がすいた私たちは木陰に腰を下ろし、持ってきたサンドイッチを広げました。大地の香りに包まれながら、三人で笑い合い、昼食を楽しみました。──その時間は、静かで心地よいひとときでした。
食べ終えてしばらくすると、急に空が暗くなり、エルビンが「ひと雨くるな」と呟きました。次の瞬間、ひんやりとした風が肌を撫で、やがて視界が真っ白になるほどの激しい雨が山を駆け抜けました。三人で小さなテントに身を寄せ、ただ雨音と風の唸りに耳を澄ませる。会話はなく、自然のリズムがすべてを支配するひとときでした。
やがて雨が上がり、光が差し戻ると、濡れたコーヒーの葉が太陽の光をはじき、畑全体が宝石のように瞬きました。その輝きには、太陽と自然の生命力が凝縮されているかのようで、農園全体から大きな力が湧き出しているのを感じました。私は心の中で「この農園のコーヒーはきっとおいしいに違いない」と確信したのです。そして同時に、この特別な一杯を日本に届けたい──そう強く願わずにはいられませんでした。
あの日の光景と感覚は、今も私の心に深く焼き付いて離れません。
日本最速への挑戦
2013年、ミエリッシュ家が初めて開催したプライベートオークション『Los Favoritos』。
ついに、憧れていた農園「Mama Mina」を日本に紹介するチャンスが巡ってきました。私はそのオークションで、Mama Minaのカツーラ・エストレージャ種を落札。わずか40kgのマイクロロットを空輸で日本へ運びました。
多数の日本のロースターが落札する中、カフェテナンゴは日本最速でこの特別なコーヒーを販売することに成功しました。
このママミナ農園のコーヒーは、カフェテナンゴにとって初めて空輸したコーヒーであり、日本最速でLos Favoritos Auctionのロットを販売したという2重の意味で記念すべきコーヒーとなったのです。
お客様にその一杯を注いだ瞬間の胸の高鳴り──それは今も鮮やかに甦ります。以来、Mama Minaはカフェテナンゴにとって、ニカラグアコーヒーを象徴する存在となっています。
つながり続けるパートナーシップ
私とミエリッシュ家の縁は2007年、エルサルバドルでカップ・オブ・エクセレンスの審査員を務めていた時に始まりました。
初めて出会ったエルビン・ミエリッシュが「今度、ニカラグアの農園を見に来ないか?」と誘ってくれたのです。まだカフェテナンゴ創業前であり、何者でもなかった私に声をかけてくれたことがとても嬉しかったことを覚えています。
その日から、友情と信頼を紡ぐ旅が続きました。彼が日本を訪れる際は必ずカフェテナンゴに立ち寄り、カウンター越しに未来を語りました。私が中米を訪ねると、畑の土を踏みしめながら収穫の喜びや新たな挑戦を分かち合いました。
そして私はママミナだけでなく、ミエリッシュ家が所有する他の農園のコーヒー豆も日本に紹介してきました。それは単なる取引を超え、彼らとともにニカラグアコーヒーの魅力を広げていく取り組みでもあります。
追記:長靴の想い出
雨の畑を歩く前に、とエルビンが私を連れて行ってくれたのは、ミエリッシュ家が支援するコミュニティの中にある小さな商店でした。ブロック塀を組んだだけの簡素な店内には、長靴や日用品がきちんと並び、土の匂いとビニールの新しい匂いが混じっていました。
彼は迷わず一番大きなサイズを選び、「これなら大丈夫だ」と笑って手渡してくれました。ところがその“最大サイズ”でさえ、私の足にはわずかに小さく、足首まで押し込むのに息を止め、脱ぐときには腰をかがめて両手で引っ張り、額に汗をにじませるほどの奮闘が必要でした。
それでも、ぬかるむ斜面であの長靴は、たしかに私の足を守ってくれた。雨粒がしみ込んだ赤土がやわらかく崩れるたび、ゴムの縁から伝わる締めつけと、エルビンの気遣いを感じていました。
帰国の朝、私はその長靴を丁寧に拭き、スーツケースの片隅にそっと収めました。サイズは合わなくても、旅の途中で授かったこの贈り物は、今も変わらず私の足もとを支えてくれている気がします。
>>>ニカラグア「ママミナ農園」購入ページ