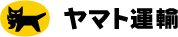2025.07.07 コーヒーの読み物
コスタリカ カップオブエクセレンス2025 全ロットカッピング

次の一杯はどこにある? ゲイシャ時代の向こう側
コスタリカのカップ・オブ・エクセレンス(COE)全ロットをカッピングしてきました。毎年この時期になると、「今年はどんな驚きがあるだろう」と胸が高鳴ります。今年も例外ではなく、驚きと発見の連続でした。
選び抜かれたロットたち
まず、今年出品されたのは115ロット。そのうち86点以上のスコアを獲得した83ロットが国内審査に進み、最終的に40ロットが国際審査へ。そして国際審査では87点以上を獲得したロットが入賞とされ、「トラディショナル・ウォッシュト」「トラディショナル・ハニー&ナチュラル」「エクスペリメンタル」の3部門から、それぞれトップ10に入った計30ロットがCOEオークションにかけられることになりました。
トラディショナル・ウォッシュト部門:ペレス・セレドンの実力
この部門の1位は、なんとペレス・セレドンにあるVista Paraiso農園のゲイシャ。コスタリカのCOEで1位といえば、これまでほとんどがタラスかウエストバレーの農園でした。それが今年はペレス・セレドン。これは正直、衝撃でした。この地域には、良いコーヒーがあるということは以前から聞いていましたが、COE1位を獲る日がくるとは思っていませんでした。
さらに驚きなのは、このVista Paraisoを所有するコラソン・デ・ヘススというマイクロミルの活躍です。このマイクロミルは、ウォッシュト部門の3位、さらにハニー&ナチュラル部門の1位までも獲得し、2冠に輝きました。
入賞ロットの内訳を見ると、10ロット中7ロットがゲイシャ。やはりこの部門でもゲイシャの強さが際立ちます。ただ、そんな中で私が注目したのは4位 モンテ・コペイの『Kizuna』ティピカ種。甘みが非常に強く、品種の持つポテンシャルが見事に表現されていました。個人的にはこうしたクラシック品種の復権に希望を感じます。
トラディショナル・ハニー&ナチュラル部門:新精製法の挑戦
この部門の1位もコラソン・デ・ヘススマイクロミルによるゲイシャ・ナチュラル「La Cusuka」。2位以下には、サン・イシドロ・ラブラドール、ロス・アンヘレス、シュマバといったコスタリカを代表するマイクロミルが並び、ランキングを見るのが楽しいです。
中でも注目は4位のシュマバ マイクロミル、El Centro農園のカツーラ種。ゲイシャやSL28が上位を占める中、唯一のカツーラでの入賞。しかも、ブラックムーン精製という新しいプロセスでのチャレンジという点も見逃せません。このカップには、丁寧な仕事と計算しつくされた実験、そしてコーヒーへの愛情が感じられました。
エクスペリメンタル部門:賛否両論の実験場
このカテゴリについては、個人的に少し複雑な想いがあります。スペシャルティコーヒーとは、土壌や気候といった「テロワール」がカップに表れることが魅力だと思っているからです。ところがこの部門では、精製によって風味が作られすぎてしまうことも多々あり、土地の個性が薄れてしまうことが多いように感じます。
とはいえ、仲の良い生産者であるラ・リアやシュマバもこのカテゴリに果敢に挑戦し、それぞれ5位(ラ・リア)、7位(シュマバ)と入賞を果たしました。創意工夫に敬意を表したいです。
ゲイシャのインフレと、その隙間から
3部門・30ロットのうち、実に18ロットがゲイシャ種。近年、他国にもみられるゲイシャ無双がここでも見られます。その特徴的で芳醇なアロマ、華やかな酸、優雅な余韻は圧倒的で、消費者受けもいい。ただ、その中に時折現れるティピカやカツーラ、カツアイといった伝統的な品種に出会うと、私は思わず背筋が伸びます。今の時代にあえてそれを選び、磨き、出品する生産者の姿勢に私は共感します。ウケの良い品種ではなく、伝統的な品種でランクインできるのは、本当に実力のある証だと思います。
追記:コスタリカのCOEにランクされるケニア品種には3種類ありますが、じつはあまり区別がはっきりとせず曖昧です。
コスタリカにおいて「Kenya」、「SL28」、「San Roque」の3つは、どれもケニア系品種。実際に作っている生産者も『種をもらった時にSL28と言われたから・・・』とかそんな感じらしいです。
終わりに
カッピングを通して強く感じたのは、スペシャルティコーヒーの価値基準が、今まさに変化のただ中にあるということです。「勝てる品種=ゲイシャ」という図式が定着する一方で、それに対する問い直しも確実に起きている。伝統的な品種や精製方法に再び光を当てようとする動き、逆にこれまでにない革新的なアプローチに挑む試み——そのどちらもが、今のスペシャルティコーヒーシーンを形作っています。
生産者も消費者も、「何をもって美味しいとするのか」「どこに価値を見出すのか」を日々探りながら、それぞれの立場で選択を重ねています。この揺らぎの中にこそまだ見ぬ「次の一杯」がある。そんな期待を持ちながら帰路につきました。